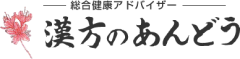新米がスーパーなどに並ぶようになってきました。
しかし、5キロ当たりが4000円を越える物ばかりで、1年前とくらべると倍ぐらいの価格になっています。
どうして米の値段が高くなってしまったのか、そしてこのまま高い状態が続くのか。
私とつながっている高次元の存在がいろいろと教えてくれることとなりました。
日本の米の流通はとても複雑で長い間、古い慣習が定着してしまいました。
なぜなのか、それは江戸時代までさかのぼることになるのです。
当時は、米の値段は米商人が決めていました。
年貢として取り立てた米を米商人が買い取っていたのです。
したがって、各藩は少しでも高く買い取ってくれる米商人を探したのです。
しかし、多くの米商人は談合していたので、ほとんど同じ値段で米を買い取っていました。
中には、新規参入するために高い値段で米を買い取る商人もいたのですが、すぐに潰されてしまったのです。
米商人の多くは大阪に集まっていて、全国の米を扱っていたのです。
藩の多くは財政が困窮していたので、新米が収穫される前にある程度収穫できる米の量を見込んで、それに相応するお金を前金としてもらっていたのです。
しかし、天候不良や洪水などで、予定通りの量が収穫できないことがあったため、不足分を翌年度に付けとして回していったのです。
それがどんどん膨れ上がってしまうことがあって、負債を抱え込んだ藩は、苦肉の策として架空の米を流通させたのです。
架空の米とは、帳簿にはあっても実際には存在しない米なのです。
どのように隠すのか、新米が収穫できた時に、過去の不足分を新米の中にあるように見せかけるのです。
つまり、米俵の中に砂を入れて、検品する時は見た目上、新米と不足分の米俵の数が合うようにさせるのです。
検品が済んで、納品する時に砂を入れた俵を抜き取るのです。
そのため、実質的には帳簿よりも少ない量の米が納品されることになるのです。
当時は、武士がそのようなことをするとは夢にも思っていなかったので、納品時に再度数量を数えることはしなかったのです。
このようなことが至る所で行われるようになり、米商人は見込み量に対する前払いに対して、高い利子を付けるようになったのです。
その結果、藩の財政はますますひっ迫して、厳しい年貢の取り立てをするようになったのです。
このような時代背景の中で、米の流通は複雑になっていったのです。
藩によっては、正規の米商人とは別に、少しでも高く買い取ってくれる裏商人と取引するようになり、多くの米が闇ルートで出回るようになっていったのです。
そのため、米の価格は高騰するようになり、一般庶民は高い米を買わされることになったのです。
そのようなことが江戸後期から慢性的に起こるようになって、幕末になると全国で米商人を襲撃する惨事が頻発するようになったのです。
歴史は繰り返すと言われますが、まさに幕末と同じような状態になろうとしているのです。
米商人に相当しているのがJAで、困窮している藩が個人の米農家なのです。
そして当時、幕府は米相場に対してはほとんど口出しはしなかったのです。
なぜなら、幕府も米商人から多額の借金をしていたので、口出しはできなかったのです。
JAは当初、個人の米農家をまとめて安定した収益を得られるために発足したのですが、組織が肥大化するようになり、金融業務や保険業務も行うようになっていきました。
農家から集めたお金を投資信託などに回すようになり、それなりの収益を上げていたのですが、バブルで負債を多く抱えこむようになったのです。
そこで、米の価格を低く抑えることで米農家への配当金を減らそうとしたのです。
米農家の収益が少ないと、JAの利益も少なくなるため、必然的に配当金は少なくなるのです。
その分を保険事業や金融業務で補おうとしたのです。
そのように仕向けたのが自民党の農水族議員と農林水産省なのです。
減反制度で米農家に補助金を出して、米農家が米をさほど作らなくても生活できるようにして、米の生産量を減らすことで米の市場をJAが独占しようとしたのです。
しかし、まじめに米を作っている農家はこれに反発して、ネット販売などで独自の販売ルートを持つようになり、JAの思うようにはいかなくなってきたのです。
JAと農林水産省は次の一手として、大規模農家を増やすと触れ回ることで、米の安定供給を確保することができることを国民にピーアールしてきましたが、現実的にはごく一部しかできないことが明るみになってきて、実情が世間に公開されるようになってきた所で、今回の米騒動となったのです。
つまり、JAと農水族議員と農林水産省が結託して、米の生産量を少なくすることでJAは米市場を独占し、農水族議員はJAを使って票集めが容易になり、農林水産省は各種の補助金制度を設けることで予算を獲得して自分たちの勢力を強めようとしていたのです。
その結果、米の自給率は低下し、次世代を担う米農家は激減し、耕作放棄地が急増しているのです。
すべてはJAと農水族議員と農林水産省の利権に個人の米農家が翻弄されてきた結果なのです。
米の価格は5キロ4000円ぐらいが妥当な価格なのですが、多くの個人農家は化学肥料や農薬、さまざまな資材はJAから購入しています。
その多くは市場価格よりも割高な物が多く、さらにJAの精米機や保冷庫の使用量も割高なため、それらの経費がすべて米の価格に上乗せされてきているのです。
さらに、米の流通ルートは多岐にわたっています。
その一部は農水族議員の親族が経営していたり、JAの幹部の親族が経営しているのです。
そのため、いくつもの米卸を経て市場に出回るため、価格は高くなってしまうのです。
小泉大臣がこのことにメスを入れようとしましたが、その強固な政治力に食い入ることはできませんでした。
まさに利権を守るための強固な壁が立ちはだかっているのです。
小泉大臣にはこの壁を崩すには、まだまだ力不足だったのです。
しかし、自民党の力も急速に衰え始めています。
公明党との連立は白紙となり、単独で衆参の過半数を取ることはできず、他の野党との連立を模索していますが、おそらく過半数を取ることはできないでしょう。
その結果、自民党の族議員の力も弱くなっていき、JAの力も急速に低下していくでしょう。
あと数年もすれば、JAは解体されて、族議員もその支持母体をなくすので落選していくでしょう。
そのような状況下で個人の米農家はどのようにしていけばいいのか、これからは大規模経営で行う農家と、小規模で行う個人農家がはっきりと分かれることになります。
小規模農家は独自の販売ルートを確立して、生産者と消費者が互いにコミュニケーションが取れるような関係が築かれていくでしょう。
自然農法が普及し、それに見合う対価を支払う人も増えていくでしょう。
さらに、消費者も農作業に関わるようになり、より自然農法が普及していくことになります。
米だけではなく、さまざまな野菜や果物もそのようになっていくでしょう。